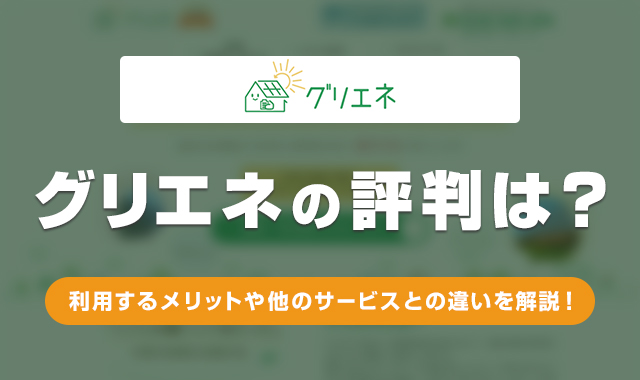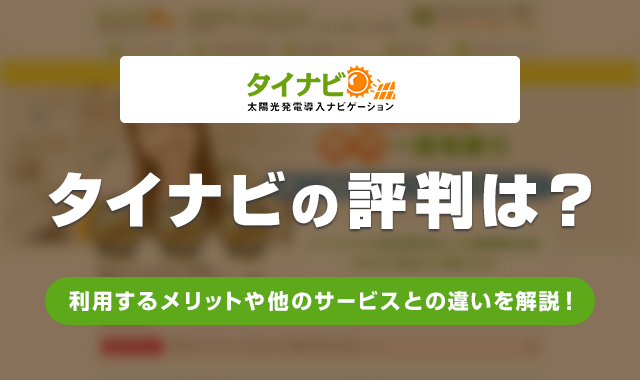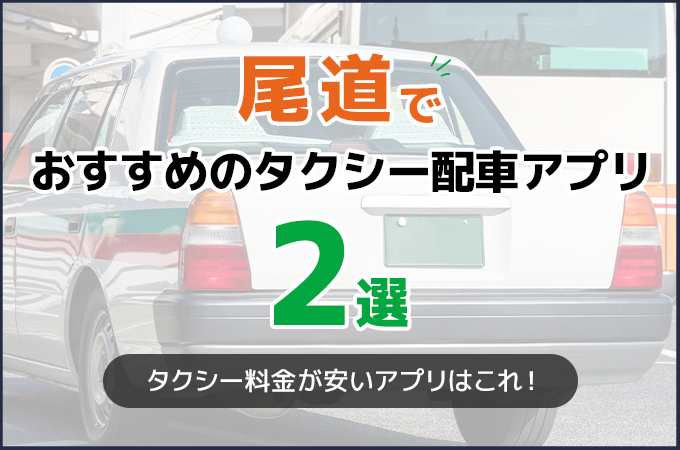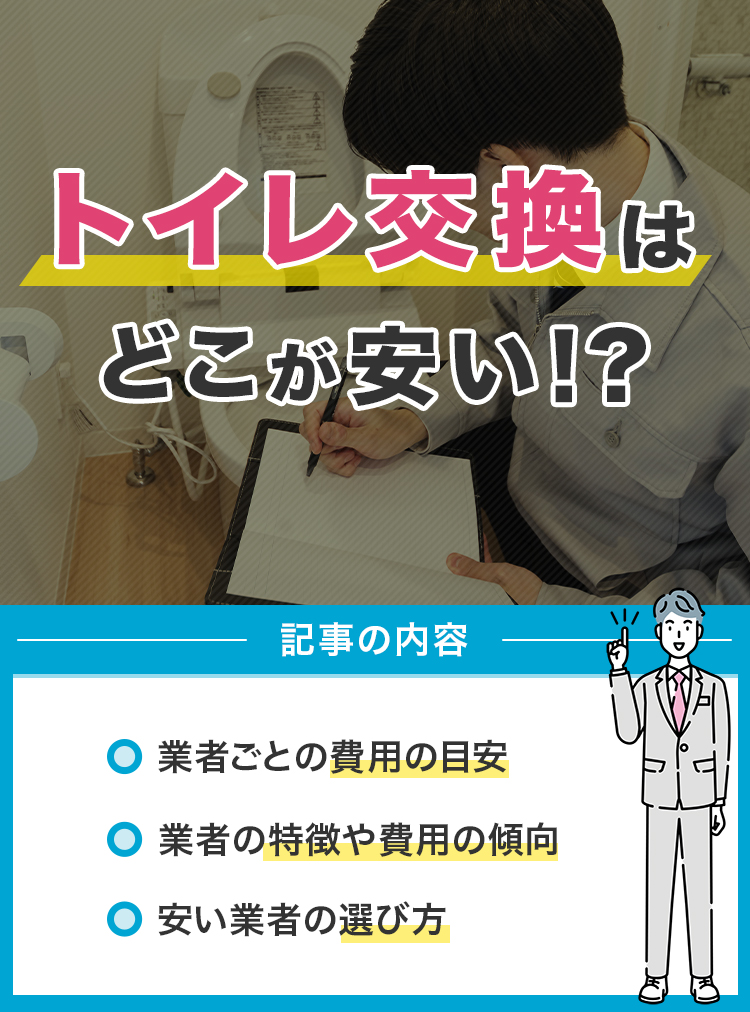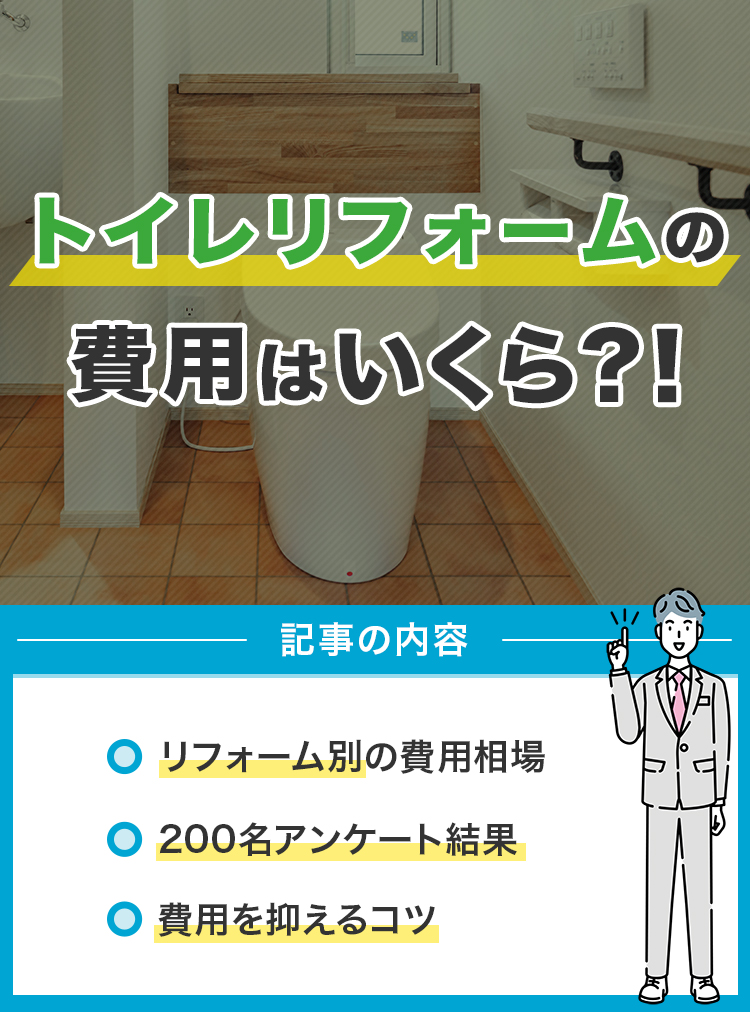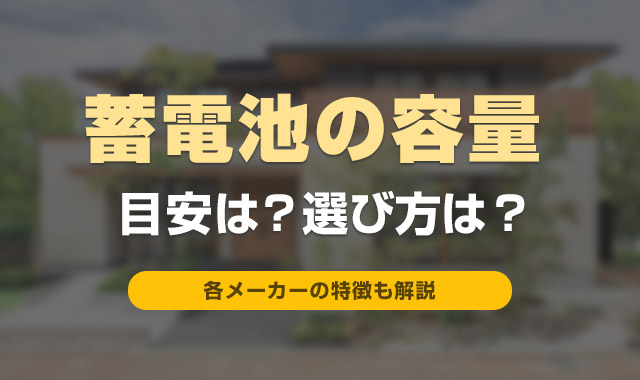
「蓄電池の容量はどう決めればいい?」
「高額なので失敗したくない…」
蓄電池は太陽光発電と組み合わせると、効率的に電力を活用できます。しかし、蓄電池の容量は様々あり、どれを選べば失敗しないか悩みますよね。
この記事では、蓄電池の容量目安や選び方・基準を解説しています。
他にも、蓄電池メーカーの特徴や蓄電池の選び方も掲載しているので、蓄電池の容量を決める際の参考にしてください。
| おすすめの太陽光発電一括見積もりサイト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ソーラー ソーラーパートナーズ |
|
|||||||||
 タイナビ タイナビ
|
|
|||||||||
| 関連記事 |
|---|
| 家庭用の蓄電池おすすめメーカー23社を比較! |

- 太陽光発電のC-clamp
- 太陽光発電システムを販売する数少ない上場企業グループ会社。独自ルートで仕入れを行っているため、販売価格の安さに強みがある。
目次
蓄電池とは?容量と出力の違いは?
充電・放電を繰り返し使える電池
蓄電池は「二次電池」ともいわれ、充電・放電を繰り返し使える電池です。放電すれば使えなくなる一次電池とは違い、二次電池には何度も充電して利用できるメリットがあります。
太陽光発電の蓄電池のほか、自動車のバッテリーやスマートフォンの電池パックなど、近年では身近なものに多く利用されているのも特徴です。太陽光発電の蓄電池には、製品に使われる材料や特徴によって鉛蓄電池やニッケル水素電池、リチウムイオン蓄電池などがあります。
「容量」と「出力」の違い
| 単位 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 容量 | kWh(キロワットアワー) | 貯められる電力量の目安 |
| 出力 | kW(キロワット) / W(ワット) | 一度に出すことが可能な電力量 |
蓄電池の容量の単位「kWh」は、その製品が貯められる電力量の目安を示すものです。蓄電池に表示されている容量を見れば、どれくらいの家電が使えるのかが分かります。
これに対して「出力」は蓄電池から一度に出すことが可能な電力量です。出力は「W」「kW」の単位で表示されます。
どれくらい貯めたいのか、というニーズは容量で判断します。停電時などに使いたい家電の目安は出力です。蓄電池を選ぶ基準となる出力と容量を確認して、ご家庭ごとのニーズに合わせて選びましょう。
容量
| 定格容量 | メーカーが規定した条件下で蓄電できる最大容量 |
|---|---|
| 実効容量 | 異なった環境下で実際に貯められる電気量 |
蓄電池の容量の表示には「定格容量」「実効容量」の2種類があります。定格容量はメーカーが規定した条件下で蓄電できる最大容量です。実行容量は、異なった環境下で実際に貯められる電気量を表しています。メーカーによっては記載がない場合もあるので注意が必要です。
蓄電池を設置する場所の環境など、諸条件によってある程度容量は変化するため、2種類の容量表示がされています。導入する際には、製品ごとに2つの容量表示を確認しておきましょう。
蓄電池は容量が増えるほど長時間使えますが、容量に比例して価格は高くなります。導入費用を抑えるには、ご家庭ごとにどれくらいの電気を貯める必要があるのかをはじめに確認しておくのがポイントです。
出力
出力の単位は「kW(キロワット)」「W(ワット)」で表示されます。電気を出す強さの単位で、「1kW=1,000W」です。これらの単位は、蓄電池が持っている家電を作動させるために必要な電力量を表示するものです。
コンセントの「合計1,000W以下」などの表示も出力を表しています。出力は電気がでるときの強さと捉えておくと良いでしょう。
家電を1kWの出力で1時間使うときの電力量は「kWh(キロワットアワー)」で表されます。これは、毎月の電気使用量を計算する際に使われていて「円/kWh」という単位で表示されています。一度にたくさんの家電を使うとブレーカーが落ちてしまうのは、家庭ごとに設けられた消費電力の出力を超えないようにするためです。
電化製品の出力の目安
| 主な家電 | 消費電力 |
|---|---|
| IHクッキングヒーター(1口) | 1800W |
| 電子レンジ | 1400W |
| 電気炊飯器 | 1300W |
| 電気ヒーター | 800~1000W |
| エアコン | 300~3200W |
| ドライヤー | 600~1400W |
| パソコン | 200~300W(デスクトップ) 60~90W(ノート) |
| 冷蔵庫 | 200~300W |
| テレビ | 40~600W |
| 扇風機 | 24W |
| スマホ充電 | 15W |
| LED電球 | 8W |
調理器具や暖房器具など、熱や冷気を直接出す仕組みの家電は出力が大きくなっています。IT調理器具や電子レンジ、電気ポット、エアコン、ドライヤーは、いずれも最高出力が1,000Wを超える高出力の家電です。一方で、テレビやパソコンの出力は1,000W以下と低くなっていますが、長時間の使用になりやすいという特徴もあります。
ただし、家電はメーカーや製品によって出力が異なるため、紹介するワット数はあくまでも目安にしてください。正確な出力を知るには、お使いの家電の表示を確認すると分かります。
家庭用蓄電池の容量を選ぶ基準は3つ
- 太陽光発電との関係で選ぶ
- 停電時の出力で選ぶ
- 深夜電力の利用で選ぶ
太陽光発電との関係で選ぶ
太陽光発電を設置済みのご家庭なら、太陽光発電システムの容量を示す「kW数」と家庭用蓄電池の関係で選ぶとよいでしょう。太陽光発電で作った電気は、一般的に3割程度が自家消費されているといわれています。たとえば、これを目安に自家消費した残りが10kWhになると予想されるなら、その分の容量を貯められる蓄電池を選ぶという選択肢です。
1日当たりの平均発電量から容量を決める
太陽光発電の平均発電量から算出するなら、1日当たりの平均発電量から自家消費分を除いて蓄電池の容量を決めます。たとえば、1日の平均発電量が12kWhなら、自家消費分の3割を引いて9kWhの蓄電池を選ぶと良いでしょう。ただし、実際の発電量は天候や設置する場所の環境によっても左右されるため、あくまでも目安として参考にしてください。
「売電」「電気を貯める」など目的で選ぶ
「売電したい」「万一のときのために電気を貯めておきたい」など目的に合わせて選ぶようにしましょう。
太陽光発電で得た電気を自家消費せずに全量を蓄電池に貯めるなら、特に大容量の蓄電池が必要です。しかし、実際には太陽光発電の容量は16kW程度が最大で、大容量になるほど容量に比例して高価になってしまいます。
売電や自家消費よりも電気を貯めるのが目的なら、10 kW程度の容量を選ぶのがおすすめです。
「非常時にどの家電を使いたいか」で選ぶ
| kWh(目安) | |
|---|---|
| 必要最小限 | 4.0kWh程度(約24時間) |
| 通常時と同程度 | 7.0kWh程度(約24時間) |
蓄電池は「停電時をどのように過ごしたいのか」という基準で選ぶのも一つの方法です。非常時にどの家電を使いたいのか、何日分を想定しておきたいのか、異なるニーズに合わせて蓄電池の容量を選びましょう。
必要最小限の家電を想定した場合
停電時に必要最小限の家電が使えればよい、とした場合の家電の例を紹介します。たとえば、冷蔵庫・照明・スマートフォン・テレビなら、1時間使用して150W程度になるのが目安です。4.0kWh程度の家庭用蓄電池であれば、これら必要最小限の家電を1日程度は使えます。
通常時と同程度の家電を使うことを想定した場合
停電時にも通常の生活と変わりなく過ごしたい場合は、使う家電を増やしていかなければなりません。たとえば、冷蔵庫・照明・スマートフォン・テレビに、エアコンとIH調理器を加えることを想定してみましょう。このケースでは消費電力の合計が2,000W程度になるため、同じ4.0kWh程度の蓄電池なら使えるのは2時間程度です。
ほかにも、電子レンジなどの高出力の家電を加えるなら、さらに必要とする蓄電池の容量はアップします。ただし、製品ごとに消費電力が異なる点には注意が必要です。
深夜電力の利用で選ぶ
深夜の電気料金が安いプランを利用すると、蓄電池を活用して電気代を節約できる可能性が高まります。深夜電力は、昼間の電気代は高めに設定されているため、昼間よりも夜間に多く家電を使う家庭に向いています。すでに深夜電力プランに契約済みであれば問題ありませんが、まだ契約していない場合にはプラン変更が必要になります。
深夜電力には様々なプランがある
| 深夜電気プラン | 特徴 |
|---|---|
| 深夜電力A | ・家族数が少ない場合や小型家電が中心 ・あまり電力を使わない家庭に向いている |
| 深夜電力B | エコキュートなど夜に電力を多く使う家庭におすすめ |
| 深夜電力C | 床暖房などもあり、深夜電力Bよりも多く電力を消費する家庭向き |
深夜電力料金が適用されるのは、夜10時から朝7時のあいだが一般的です。深夜電力プランが適用される時間帯は、電力会社によって異なるため契約プランごとに確認しましょう。
深夜電力プランには、使う家電の種類や電力量に応じていくつかのパターンがあります。たとえば、深夜電力Aは家族数が少ない場合や小型家電が中心で、あまり電力を使わない家庭向きです。深夜電力Bは、エコキュートなど夜に電力を多く使う場合に向いています。深夜電力Cは、床暖房などBよりも多く電力を消費する家庭に最適なプランです。
料金の見直しもチェックしておこう
深夜電力プランは、電気量単価について各電力会社で見直しが行われました。見直し後は昼間の料金単価を従来よりも安く、夜間は高く設定しています。昨今の電力需要が日中と夜間の使用料にあまり差がなくなってきたことを受けて変更されました。
これによって、深夜電力の昼間と夜間の料金の差は従来よりも少なくなりました。すでに契約していれば契約時点の単価はそのまま適用されますが、新規契約の場合は新しい単価が適用されます。電力会社によって新しい深夜電力プランの契約内容は異なるため、要件などを確認しておきましょう。
| おすすめの太陽光発電一括見積もりサイト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ソーラー ソーラーパートナーズ |
|
|||||||||
 タイナビ タイナビ
|
|
|||||||||
家庭用蓄電池の選び方5つ
- 蓄電池の容量で選ぶ
- ライフスタイルで選ぶ
- 蓄電池の寿命で選ぶ
- 保証期間の長さで選ぶ
- 蓄電池のサイズで選ぶ
蓄電池の容量で選ぶ
製品の容量を目安に決めるのは、蓄電池を選ぶのに分かりやすい選択方法です。各メーカーでは数kWから大容量までさまざまな製品を販売しています。蓄電池を容量によって選ぶ場合、同じメーカーでも製品ごとに容量が異なる点に注意が必要です。
メーカーによって容量は異なる
近年ではリチウムイオン電池を使った蓄電池が主流ですが、蓄電容量や実行容量(実際に使える容量)はメーカーによって違います。容量が同じ程度の製品でも、通常は1日1回の充放電のところ、2回の充放電が可能な製品もあります。容量に加えて、製品ごとのスペックもよく確認することも必要です。
まずは使用する電力量を算出する
蓄電池の容量は大きいほど貯められる電力量は増えますが、大容量になれば予算オーバーになる可能性もあります。使う電力量を算出して必要な蓄電池の容量を決めてから、メーカーごとの容量表示を確認しましょう。
業者に蓄電池の選び方を相談する際にも、容量の基準が決まっているほうがニーズに合う製品を検討できるので安心です。
ライフスタイルで選ぶ
蓄電池はライフスタイルを基準に選ぶのがおすすめです。なかでも、太陽光発電の余剰電力と深夜電力の、どちらを活用するかでも選ぶ基準は変わります。太陽光発電や蓄電池の使い方によって、ご家庭で必要とする蓄電池の容量も変わるからです。
電力量の目安を知る
家庭で消費する電力量と、余剰電力量がどれくらいなのかを目安にして選ぶことができます。普段使っている家電の消費電力や多く使う時間帯も考慮して選ぶことも必要です。太陽光発電で発生した電気のうち、自家消費した残りを蓄電池に貯めるなら、それほど大きな容量でなくても大丈夫でしょう。
ライフスタイルの変化も見据えておく
「退職して日中家にいるようになった」「子どもが大きくなったので、仕事復帰した」など、ライフスタイルが変化していくことも考えられます。予想されるライフスタイルも見据えながら、計画的に蓄電池の容量を決めることをおすすめします。
昼間よりも安い深夜電力を蓄電池に貯める場合は、十分な電力量を蓄電できるよう大きめの製品のほうが向いています。安い夜間電力を貯めておけば、日中でもお得に家電を使えるでしょう。
蓄電池の寿命で選ぶ
リチウムイオン蓄電池の寿命は、一般的には15~20年といわれています。容量が大きいほど長い時間使えるため、充電回数が少ない分劣化しにくく長寿命です。蓄電池の寿命は、主に「サイクル数」と「使用期間」で判断します。
寿命の目安は15~20年程度
使用期間は、製品を使い始めてから寿命までの期間で15~20年程度です。サイクル数は充放電の回数で、製品が何サイクルで性能が劣化するのかが寿命の目安です。一般的にリチウムイオン蓄電池の場合は6,000~1万回程度で、製品の仕様書などに記載されています。
環境や使い方で寿命は変わる
蓄電池の寿命はおおまかな目安にはなりますが、設置する環境や使いかたなども影響するのですべて同じとはいえません。また、寿命がくればすぐに使えなくなるというわけでもなく、性能がある程度劣化しても長く使える場合もあります。
保証期間の長さで選ぶ
希望する保証期間の製品を選ぶのも蓄電池の選び方の一つです。蓄電池の保証書には保証期間が記載されているので、検討している製品の保証期間を確認しておきましょう。
蓄電池の保証期間は10~15年程度
蓄電池の保証期間は10~15年程度が一般的です。製品によって10年間は無償で保証を提供し、有償で15年保証を選べるものもあります。保証期間を延長して安心して使いたい場合は有償にするなど、ニーズに合わせて選ぶことも可能です。
そのほかの保証サービスもチェックしよう
保証期間はメーカーによって異なるほか、保証内容などの詳細も各メーカーで特徴を打ち出しています。インターネットを使った見守りサポートやモニタリングなど、さまざまなサービスがあります。長期間に渡って使用するのが蓄電池なので、納得できる保証期間や保証内容のものを選びましょう。
蓄電池のサイズで選ぶ
蓄電池を設置するためには一定のスペースが必要になります。そのため、あらかじめ蓄電池のサイズを確認して、設置可能な製品を選ぶことが大切です。蓄電池自体の大きさに加えて、作業するための広さも確保する必要があります。
蓄電池には屋内型と屋外型、どちらにも置ける両用タイプがあります。大型で屋外のみに設置するものや、マンションにも設置可能なコンパクトサイズのものなど、蓄電池のサイズはさまざまです。設置可能なものを選ぶために、事前にサイズを測ってもらうようにしましょう。
【メーカー別】蓄電池の特徴
パナソニック
- 高い安全性
- 15年の長期保証(10年まで無償)
- 最大33.6kWhまで増やせる
パナソニックは、ご家庭のライフスタイルや環境に合うよう多彩な製品を展開しています。歴史と技術に裏付けされた信頼性の高い商品です。すべての工程を自社で製造し、多重保護設計による高い安全性を誇っています。製品保証は10年が無償、有償なら15年という長期保証なので安心して長期間使用できるのも特徴です。
「住宅用創蓄連携システムS+」は、ニーズに合わせて3.5 kWhまたは5.6kWhの容量を選べます。さらに、蓄電池を複数組み合わせることで最大33.6kWhまで容量を増やすことも可能です。停電時には、冷蔵庫や照明などのほか、電気ケトルや炊飯器も使えます。200V(ボルト)トランスを追加で設置すれば、出力が2倍になりエコキュートなど200Vの家電も使用可能です。
シャープ
- 4.2~9.5kWhまで選べる容量
- 15年の長期保証(10年まで無償)
- 浸水しにくい設計
シャープの「クラウド蓄電池システム」には、コンパクトタイプ・ミドルタイプ・大容量タイプの3種類があります。ニーズに合わせて4.2~9.5kWhまでの容量を選ぶことが可能です。コンパクト設計なので、屋外設置でも簡易基礎でスピーディーに設置できます。無償で10年保証、有償での15年保証が付いているので安心して使えるでしょう。
9.5kWhと大容量の「JH-WB2021」は、太陽光発電で作った電気をたくさん貯められます。停電時には分電盤から家中に電気が供給される「全負荷型」のため、普段と同じ生活が可能です。また屋外、屋内どちらにも設置できるタイプなので設置場所を選びません。製品本体の底にネジがない設計のため内部に浸水しにくいのもメリットです。
京セラ
- 長寿命を実現
- 機器・自然災害・出力のトリプル保証(有償)
- 大容量でもコンパクト設計
京セラは1984年にソーラーエネルギーセンターの設立以降、太陽光発電の開発を進めてきました。厳しい品質管理と確かな技術で製品の長寿命を実現しているメーカーです。機器の生産から施工、メンテナンスまでをトータルで行っています。太陽光発電システムのトリプル保証(有償)では、機器15年、自然災害15年、出力15年をセットで提供しているのも特徴です。
「EGS-LM1201」の容量は、12.0kWhと家庭用蓄電池のなかでも特に大容量を誇っています。貯められる電気は大容量でも、本体サイズは薄型で奥行きは30cmとコンパクト設計で、狭いスパースでも設置しやすいというメリットがあります。停電時には事前に設定しておいた家電へ電気を自動供給でき、電力の合計が430W程度であれば最大で23時間の使用が可能です。
オムロン
- 遠隔モニタリングサービス利用で15年保証
- 小容量でも1日2サイクル以上可能
- 地震や浸水に強い設計
オムロンはパワーコンディショナを開発してきたパイオニアとして、今日まで創エネルギー分野での実績を積み重ねてきました。蓄電池は家庭のライフスタイルに応じて選べるよう、4種類の容量の製品を販売しています。KPAC-Bシリーズは有償の「遠隔モニタリングサービス」に申し込むと15年保証が付きます。遠隔モニタリングサービスは、スマートフォンなどから蓄電池の状況を24時間監視してくれるサービスです。
KPAC-Bシリーズ「KPAC-B25」の容量は4.2kWhです。少ない容量のようですが、実際には1日に2サイクル以上使えるため、8.4kWh程度の製品と同じように活用できます。コンパクトな屋内設置型で地震にも強い設計になっています。屋内設置タイプなので、万一水害による床下浸水が起こっても安心です。
ニチコン
- 家庭用蓄電池販売数が国内トップクラス
- ポータブルタイプも販売している
- 蓄電量の30%を非常用に常時残すシステム
ニチコンは、家庭用蓄電池の販売数が国内トップクラスのメーカーです。一般的な家庭用蓄電池のほかに、工事が不要で簡単に設置できるポータブルタイプの蓄電池も開発・販売しています。急な停電時には、事業所・一般家庭のどちらもコンセントに差し込むだけで活用できるのが「ESS-P1S1」です。2kWhと小型ですが、停電しても重要なデータの保護や電動ベッドの作動など緊急用の電源に使えます。
「ESS-U2M1」は11.1kWhの大容量なので、停電時には照明や冷蔵庫のほか、テレビやスマートフォンの充電など最大24時間程度使えます。貯めた電力の30%は、非常時用として常に残しておく仕組みなので安心です。室内リモコンをインターネットに接続すれば、サーバーが24時間チェックして、分析やメンテナンスなどを行います。
伊藤忠商事
- 次世代蓄電システム「Smart Starシリーズ」を開発
- AIによる最適制御機能を搭載
- 「環境価値ポイント」を付与している
伊藤忠商事は創エネルギーの推進を目指し、次世代蓄電システム「Smart Starシリーズ」を開発・販売しています。株式会社NFブロッサムテクノロジーズと共同の「Jアライアンス」として開発・製造を行ってきました。2019年から順次FITが終了していくなか、蓄電池の需要が高まっている情勢に向けたものです。太陽光発電の電気を自家消費するためにも蓄電池の活用が必要としています。
「SmartStar3」は、シリーズの大きな特徴である「AIによる最適制御機能(GridShare)」を搭載した最新型です。13.16kWhの大容量なので、停電時や自家消費に多くの電気を貯めておけます。世界初となる「環境価値ポイント」は、太陽光発電の自家消費分に対して付与されるものです。蓄電池を活用することがお得になる仕組みとして注目されています。
家庭用蓄電池のメリット3つ
- 災害時でも使用できる
- 電気料金を安くできる
- 補助金を利用できる
災害時でも使用できる
蓄電池には、近年多発する地震や豪雨などの自然災害による停電時にも電気が使えるメリットがあります。万一停電になっても蓄電池があれば、貯めておいた電気で家電を使い普段と変わらない生活が可能です。太陽光発電と組み合わせれば、長期間の停電にも対応できます。
蓄電池には事前に使いたい家電を設定する特定負荷型と、自動的に家中のコンセントに電気が供給される前負荷型があります。蓄電池を選ぶ際には、どちらが家庭のニーズに合っているのかを検討しましょう。
電気料金を安くできる
家庭用蓄電池と太陽光発電を組み合わせると、自家発電した電気を蓄電池に貯めて活用することで電気代を節約できます。また、太陽光からの発電がない場合に備えて、自家消費した残りを蓄電池に貯めておけば電力会社から買電しなくてすみます。
太陽光発電がない場合でも、安い深夜電力を貯めて昼間に使えば電気料金を抑えることが可能です。ライフスタイルに合わせて、いろいろな節約方法を使い分けられるのが蓄電池のメリットです。
補助金を利用できる
蓄電池の導入には、国や地方自治体の補助金を受けられることがあります。蓄電池は初期費用が高額になりやすいため、補助金の条件を確認して申請し導入費用を抑えるようにしましょう。
国の補助金は一般社団法人「環境共創イニシアチブ」が実施しています。毎年補助金の内容が変わるため、その都度確認することが必要です。地方自治体の補助金の場合は、自治体によって条件や補助額は異なります。どちらも申請期間が定められていて、予算額の枠が埋まれば募集は終了するので早めに申請しましょう。
家庭用蓄電池のデメリット3つ
- 価格が高い
- 寿命がある
- 設置するスペースが必要
価格が高い
蓄電池は決して安い機器ではありません。蓄電池は値段が高く、本体と工事費込みで約100~200万円が相場です。導入後は電気代を節約できますが、初期費用が高い点はデメリットでしょう。特に、たくさん電気を貯めたい場合に容量の大きな蓄電池を購入すれば、容量に比例して価格は高額となります。
寿命がある
蓄電池は使い捨てではなく繰り返し充放電できますが、永遠に使えるものでもありません。充放電を1回行うと1サイクルで、寿命の目安になる使用可能なサイクル数は仕様書に表示されています。
1日1サイクル使った場合の使用可能な年数は、リチウムイオン蓄電池の場合には10~15年程度とされています。蓄電池に寿命があるのは確かにデメリットですが、寿命が来れば使えないわけではなく、少しずつ劣化していくと捉えておくとよいでしょう。
設置するスペースが必要
家庭用蓄電池を設置するには、製品のサイズに合うようなスペースが必要です。特に屋外の場合には、日差しの当たるような高温の場所を避けるなど、設置する環境にも配慮しなければなりません。また、周囲にはモノを置かない、結露する場所は避けるといった条件もあります。
屋内でも製品によっては周辺機器が必要な場合もあります。家庭の環境に合わせて、設置可能なスペースを事前に確保することが必要です。蓄電池を設置する際には、施工業者にスペースが適切かどうかを事前に確認しておきましょう。
まとめ:蓄電池の容量は目的によって選ぼう
蓄電池を選ぶときのポイントは、はじめに設置する目的を決めておくことです。容量を決める主な基準には、太陽光発電との組み合わせかたや夜電力プランの活用、停電時の家電の使い方などがあります。
蓄電池は容量に比例して価格が高くなるため、導入費用を抑えるには必要な容量を算出しておくことも大切です。普段使っている家電や停電時に使いたい家電の消費電力を把握し、適切な容量の蓄電池を選びましょう。