外構工事の耐用年数と国税庁が定める減価償却できる期間
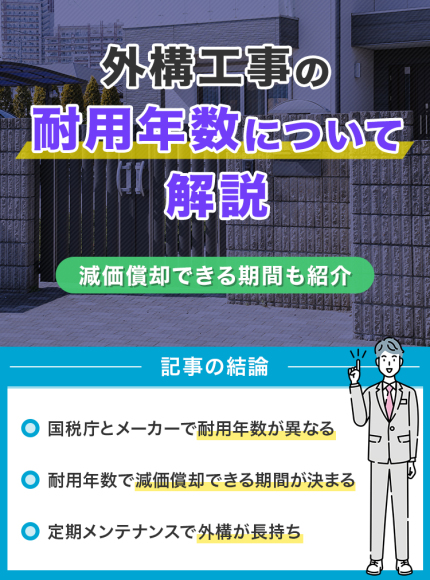
「外構工事の耐用年数はどれぐらい?」
「国税庁とメーカーが決めた耐用年数って違うの?」
外構やエクステリアの工事をしたい時に耐用年数が気になりますよね。工事の場所や素材によっても変わるので具体的な年数がどのぐらいなのか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外構エクステリア工事の耐用年数を国税庁が定めた法定耐用年数を元に、素材別に解説いたします。
さらに国税庁とメーカーの耐用年数の違いについても紹介しているので外構やエクステリア工事に取り組む前にぜひ参考にしてください。
- 【PR】タウンライフ
-
- 初めて外構工事をするならタウンライフ
-

タウンライフとは?
- 「プラン作成」「見積もり作成」「アイデア&アドバイス」を無料で提供
- 11周年の安心と実績
- 自社の厳しい審査をクリアした650社以上の企業が掲載
初めての外構工事で業者選びに迷っている方は、タウンライフを利用しましょう。施工箇所や予算を入力すると、おすすめの外構業者を複数紹介してくれます。
見積もりからプランニングまですべて無料で利用できます。業者選びで失敗したくない人は、見積もりを簡単に比較できるタウンライフを利用しましょう。
\利用満足度ナンバーワン! /
目次
外構工事の耐用年数とは?

国税庁(財務省)とメーカーで耐用年数が異なる
耐用年数とは固定資産として使用できる期間を指し、国税庁が定めた法定耐用年数とほぼ同じ意味です。
耐用年数は、固定資産の価値が減少する期間を示す重要な指標で、それに基づき減価償却が行われますが、国税庁(財務省)とメーカーで耐用年数が異なる場合があります。
耐用年数はあくまでも目安
国税庁とメーカーが定めた耐用年数耐用年数には違いがあり、事業などで減価償却をおこなう場合は法定耐用年数を採用します。法定耐用年数を超えても使用できなくなるわけではなく、あくまでも目安として捉えておきましょう。
個人宅の場合
個人宅の戸建ての耐用年数は、石造は35年、鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造は30年、土造は20年、コンクリート造は15年、木造や金属造は10年です。
メンテナンス状態によっても寿命は変わりますが、法定耐用年数が一般的な寿命の目安とされています。
商業施設やマンションなど
鉄筋コンクリート造商業施設やのマンションの法定耐用年数は1998年の税制改正で47年と定められています。この耐用年数は減価償却の計算基準であり、建物の性能や寿命を示すものではありません。
国税庁とメーカーの耐用年数の違い

国税庁と財務省の耐用年数
国税庁から【主な減価償却資産の耐用年数表】が、財務省からは【耐用年数についての論点の整理】が発表されています。詳しい外構工事で使用する素材の耐用年数や論点を知りたい方はこちらを参考にして下さい。
▶国税庁の耐用年数表はこちら
▶財務省の耐用年数についてはこちら
国税庁が定める外構工事の法定耐用年数カテゴリー
| 用途 | 広告用、舗装道路、競技用施設、緑化施設など |
|---|---|
| 構造 | 素材ごとに鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造、土造、金属造、合成樹脂造、木造など |
国税庁が定める外構工事の法定耐用年数のカテゴリーは、「構造物」として分類され、それがさらに「用途」と「構造」に細かく分けられています。
「構築物」は屋外に設置されるもので、建物は屋内に設置されるものと区別されます。駐車場や舗装道路、庭園なども、外構工事が施されれば「構築物」に該当し、それぞれに法定耐用年数が設定されています。
メーカーの耐用年数
耐用年数は法定耐用年数を指すため、各メーカーが定めた耐用年数は「耐久年数」と表記されています。
耐久年数はメーカーが耐久テスト等を経て、その商品が実際に使用できるであろう期間を指します。
実際に外構やエクステリア工事をおこなう際、使用できる期間を知りたい場合は、各メーカーの発表する耐久年数を確認してください。
外構工事の減価償却とは?

耐用年数によって減価償却できる期間がきまる
減価償却をする際は、国税庁が定めた法定耐用年数を用いて会計処理を行います。メーカーが定めた耐用年数はあくまでも耐久年数であり、減価償却には用いることができません。
外構エクステリア工事は減価償却が可能
外構エクステリア工事にかかった費用は減価償却が可能です。仕事場を自宅兼事務所にしている場合など、外構エクステリア工事にかかった費用を経費にすることもできます。
減価償却できるものとできないもの
自身で減価償却処理することも可能ですが、外構に用いる素材や使用目的によって法定耐用年数や勘定科目が異なり減価償却できないものもあります。知識がない場合は税理士等の専門家に相談しましょう。
【種類別】外構エクステリア工事の耐用年数
| 施工場所 | 耐用年数 |
|---|---|
| カーポート | 15年 |
| 駐車場 | 10~15年 |
| 自転車置き場 | 10~15年 |
| 塀 | 10~35年 |
| フェンス | 素材によって異なる |
| 門扉 | 10~35年 |
| デッキ・テラス | 5~20年 |
| 庭 | 10~20年 |
| アプローチ | 15年 |
外構・エクステリア工事の耐用年数を施工場所別に見ていきます。耐用年数は素材や状況によって異なるため、あくまでも参考程度にしてください。
カーポートは15年
カーポートの耐用年数は15年ですが、法定耐用年数は45年です。管轄の税務署長へ耐用年数の短縮制度の適用を申請することで15年に短縮できる可能性があります。
駐車場は10年~15年
| 構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 青空駐車場 | 土地のため耐用年数なし |
| アスファルト | 10年 |
| コンクリート | 15年 |
駐車場の耐用年数は10年~15年です。駐車場の塗装は種類によ耐用年数が変わりアスファルトは10年、コンクリートは15年です。
青空駐車場は構築物ではなく土地で耐用年数は無く、耐用年数が設定されていないので減価償却することもできません。
自転車置き場は10年~15年
| 素材 | 耐用年数 |
|---|---|
| 合成樹脂 | 10年 |
| 金属製 | 15年 |
| アスファルト | 10年 |
| コンクリート | 15年 |
自転車置き場の耐用年数は10年~15年です。素材により異なり、合成樹脂を用いた屋根は10年、金属製による屋根など日除け設備の場合は15年です。
自転車置き場の地面も、舗装素材によって耐用年数は異なりアスファルト10年、コンクリート15年です。
塀は10年~35年
| 素材 | 耐用年数 |
|---|---|
| コンクリート | 15年 |
| 鉄筋コンクリート | 30年 |
| 木造 | 10年 |
| 石造 | 35年 |
塀の耐用年数は10年~35年です。素材によって異なりコンクリート15年、鉄筋コンクリート30年、木造10年、石造35年です。
フェンスは素材によって異なる
| 素材 | 耐用年数 |
|---|---|
| スチール製 | 15年 |
| 金属製 | 10年 |
| 木製 | 10年 |
| アルミ製 | 定めなし |
フェンスの耐用年数は素材によって異なります。一般的にフェンスはアルミ製が多く使用されています。
アルミ製は錆びにくく丈夫で、具体的な耐用年数はなく半永久的に使用可能のため法定耐用年数は定められていません。スチール製は15年、金属製や木製は10年です。
門扉は10年~35年
| 素材 | 耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 10年 |
| コンクリート | 15年 |
| 石造 | 35年 |
門扉の耐用年数は10年~35年です。素材によって異なり、石造は35年、コンクリートは15年、木造は10年です。
デッキ・テラスは5年~20年
| 素材 | 耐用年数 |
|---|---|
| 天然木 | 5年~15年 |
| 人工木 | 20年 |
デッキ・テラスのの耐用年数5年~20年です。素材によって異なり、天然木は5年〜15程度、人工木は20年です。
庭は10年~20年
| 素材 | 耐用年数 |
|---|---|
| 人工芝 | 10年 |
| 砂利 | 15年 |
| 庭木 | 20年 |
庭の耐用年数は10年~20年です。庭木は庭園なので20年、砂利は構築物なので15年です。
人工芝の場合、表面部分と基礎部分では素材が違うため耐用年数が異なります。直接触れることの多い、表面部分の突起部分(ターフ)とアンダーパットは「構築物」の「合成樹脂造のもの」に該当するため、耐用年数は10年です。
アプローチは15年
| 素材 | 耐用年数 |
|---|---|
| コンクリート | 15年 |
| 石敷 | 15年 |
| レンガ | 15年 |
アプローチの耐用年数はコンクリート、石敷、レンガ共に15年です。
外構を長持ちさせるなら定期メンテナンス

外構は雨風の影響を受けやすいので少しでも長持ちさせるためには定期的なメンテナンスが必要です。耐用年数はあくまでも目安であり、耐用年数の範囲内であっても、劣化し使えなくなる可能性もあります。
- ブロック塀などにひび割れがないか
- デッキに腐敗や塗装が剥がれた箇所があるか
- 屋根の柱がぐらついていないか
- 庭木が枯れたり害虫が付いていたりしないか
- 埃や錆が付着していないか
この様な事をチェックし定期的にメンテナンスを行いましょう。ブロック塀のひび割れなどは素人が補修しようとしても危険なため、プロに依頼すると外構を長持ちさせるメンテナンスを受ける事ができます。
メンテナンス時期の目安
外構・エクステリアには場所や素材ごとに寿命があります。外構工事後にそのままの形状を保つことは非常に難しいです。
素材ごとに寿命がありますが一定期間ごとにメンテナンスを行う事で使いやすく、おしゃれな外構エクステリアを保てます。
例えば5年、10年、15年ごとに専門の業者による定期的な点検やメンテナンスを行えば設置場所の環境や使用頻度による予期せぬ劣化を早期に察知し、修繕費用を節約する事にも繋がります。
外構工事の業者を選ぶポイント

選ぶポイント
- 工事内容にあった業者を選ぶ
- 公式サイトに施工事例を多数掲載している
- 保証やアフターサービスが多い
- 見積書に金額の明細が明記されている
- 一括見積もりサイトで複数の業者を比較する
工事内容にあった業者を選ぶ
信頼できる外構業者を選ぶコツは、工事内容にあった業者を選ぶことです。業者によって工事内容に得意不得意があり、経験の少ない工事の場合は外注することもあり、費用や仕上がりに不安に感じることもあります。
依頼したい工事内容を得意としているか調べる方法は、業者に直接確認したり、公式サイトに掲載している過去の施工例を確認しましょう。依頼したい工事の施工例が多く掲載されている場合、経験豊富である証拠です。
公式HPに施工事例が多い業者を選ぶ
信頼できる外構業者は、公式サイトに多数の施工事例を掲載しています。施工事例が多いということは、多くの工事を受けているだけでなく、仕上がりにも自信があるということです。
また、掲載された施工事例を見ることで、業者がどのようなデザインや技術を持っているのかを事前に確認できます。業者に相談する前に施工事例をみて、どのような外構にしたいかイメージを固めておきましょう。
保証やアフターサービスが多い
信頼できる外構業者を見分ける方法は、保証やアフターサービスが豊富に用意されているかを確認しましょう。アフターサービスが工事価格に含まれており、追加料金がかからない外構工事業者が理想的です。
保証やアフターサービスを確認する際、工事内容に適した保証がある、かつ保証期間が長い業者を選ぶのが好ましいです。業者選びに悩んだら、一括見積もりサイトで複数の業者から詳細を取り寄せ、保証内容を比較してみましょう。
見積書に金額の明細が明記されている
信頼できる業者は、見積書に金額の明細が記載されているかでも判断可能です。信頼できる業者は、工事にかかる金額はもちろん、対応する面積や単価、工事に必要な備品等の数など、見積もり書に詳細に記載してくれます。
一方で「工事一式」や「諸経費」というワードが見積書内にある場合は注意が必要です。見積書に工事一式や諸経費のワードがある場合は、担当者に内訳を確認することで、業者選びに失敗する可能性を少なくできます。
一括見積もりサイトで複数の業者を比較する
業者選びに悩んだ場合は、一括見積もりサイトを利用し、複数の業者を比較しましょう。一括見積もりサイトを利用すると、費用やサービス内容などの情報を調べる手間が省け、自分にあった業者を探しやすいです。
一括見積もりサイトは、多くの業者から連絡がくるから苦手という人は、タウンライフの一括見積もりを利用しましょう。自分の気になる業者にのみ見積もり依頼が出来るため、業者からの連絡を極力減らせます。
一括見積もりのメリット

外構工事の業者を選ぶ際、必ず見積もりを取りましょう。外構工事業者を探し全て自分で見積もりを依頼するのは、工程数が多く疲弊してしまいますよね。
どこの業者から見積もりを取ればいいのかわからないときは、一括見積もりができるサイトを利用するのは賢い選択です。
タウンライフでの一括見積もりは、質問に答えるだけで独自の厳しい基準をクリアした約620社の中から希望の工事内容に合った外構工事業者をピックアップできます。資料請求を簡単に行えるだけでなく、たった3分で複数の業者から簡単に見積もりを取れます。
外構工事の耐用年数でよくある質問
外壁塗装の耐用年数は何年ですか?
外壁塗装の耐用年数は一般的に10~20年が目安ですが、使用する塗料や外壁材、建物の立地条件によって変わります。具体的には、ウレタン塗料は6~10年、フッ素塗料は10~20年、シリコン塗料は8~15年がそれぞれの耐用年数とされています。
個人事業主の場合、外構工事を経費で落とすことはできますか?
物置は「建物勘定」、カーポートと土間工事は「構築物勘定」に分類され、それぞれ減価償却が適用されます。資産の減価償却は、用途や構造に応じて省令耐用年数表から計算する方法が一般的です。これらの資産には固定資産税が課税されるため、詳しくは自治体で確認してください。
外構エクステリア工事は減価償却が可能|メンテナンスで長持ち

外構・エクステリア工事の耐用年数は、国税庁とメーカーでは異なるので、減価償却をする際は、国税庁が定めた法定耐用年数を用いて会計処理を行いましょう。
施工場所や素材だけではなくメンテナンスの状況や使用状況も耐用年数に影響を与えます。
プロに依頼することで、外構を長持ちさせるメンテナンスを受けられます。どんな外構工事業者を選べばよいかわからない時には一括見積を利用すると良いでしょう。
- 【PR】タウンライフ
-
タウンライフなら初めての外構工事も安心!

初めて外構工事をするなら、完全無料のタウンライフ一括見積もりがおすすめです。優良外構業者650社から比較ができるので、外構工事の最新相場がわかります。
参考資料
| 参考サイト | URL |
|---|---|
| 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定) | https://www.chord.or.jp/index.html |
| 国民生活センター | https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html |
| 特定商取引法ガイド | https://www.no-trouble.caa.go.jp/ |
初めての外構工事でおすすめの記事
| 編集部が選ぶおすすめ記事 | |
|---|---|
 ガーデンプラス評判 ガーデンプラス評判 |
 外構の見積もりの取り方 外構の見積もりの取り方 |
 タウンライフ評判 タウンライフ評判 |
 外構工事の費用相場 外構工事の費用相場 |
 手入れ不要の庭DIY 手入れ不要の庭DIY |
 外構がしょぼい理由 外構がしょぼい理由 |
 外構工事で使えるローン 外構工事で使えるローン |
 外構DIYおすすめ7選 外構DIYおすすめ7選 |
 カーポート値段相場 カーポート値段相場 |
 ウッドデッキ費用相場 ウッドデッキ費用相場 |
 目隠しフェンス費用相場 目隠しフェンス費用相場 |
 おしゃれな駐車場 おしゃれな駐車場 |
地域別おすすめ外構業者
北海道・東北エリア
| 北海道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 千歳市 | 江別市 | |||
| 旭川市 | 函館市 | 北広島市 | |||
| 苫小牧市 | 北見市 | 帯広市 | |||
| 恵庭市 | |||||
| 青森県 | |||||
| 青森市 | 八戸市 | 弘前市 | |||
| 三沢市 | |||||
| 秋田県 | |||||
| 秋田市 | 横手市 | ||||
| 岩手県 | |||||
| 盛岡市 | 奥州市 | 北上市 | |||
| 山形県 | |||||
| 山形市 | 鶴岡市 | 酒田市 | |||
| 福島県 | |||||
| 郡山市 | いわき市 | 福島市 | |||
| 白河市 | 須賀川市 | 会津若松市 | |||
| 宮城県 | |||||
| 仙台市 | 大崎市 | 石巻市 | |||
| 名取市 | 登米市 | ||||
関東エリア
| 東京都 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 杉並区 | 練馬区 | |||
| あきる野市 | 八王子市 | 町田市 | |||
| 日野市 | 足立区 | 府中市 | |||
| 江戸川区 | 大田区 | 中央区 | |||
| 小金井市 | 青梅市 | 葛飾区 | |||
| 三鷹市 | 多摩市 | 調布市 | |||
| 稲城市 | 小平市 | 立川市 | |||
| 板橋区 | 西東京市 | 墨田区 | |||
| 東村山市 | 国立市 | 清瀬市 | |||
| 狛江市 | 品川区 | 北区 | |||
| 東大和市 | 豊島区 | 国分寺市 | |||
| 文京区 | 目黒区 | 江東区 | |||
| 中野区 | 荒川区 | ||||
| 神奈川県 | |||||
| 横浜市 | 相模原市 | 藤沢市 | |||
| 厚木市 | 横須賀市 | 武蔵野市 | |||
| 平塚市 | 川崎市 | 大和市 | |||
| 秦野市 | 小田原市 | 鎌倉市 | |||
| 伊勢原市 | 綾瀬市 | 海老名市 | |||
| 座間市 | |||||
| 埼玉県 | |||||
| 加須市 | 深谷市 | 鴻巣市 | |||
| 草加市 | 上尾市 | 越谷市 | |||
| 幸手市 | 川口市 | 桶川市 | |||
| 三郷市 | さいたま市 | 熊谷市 | |||
| 久喜市 | 川越市 | 狭山市 | |||
| 入間市 | 新座市 | 所沢市 | |||
| 行田市 | 羽生市 | 蓮田市 | |||
| 富士見市 | 八潮市 | 春日部市 | |||
| 本庄市 | 日高市 | 飯能市 | |||
| 戸田市 | 朝霞市 | ふじみ野市 | |||
| 和光市 | 北本市 | 吉川市 | |||
| 東松山市 | |||||
| 千葉県 | |||||
| 千葉市 | 柏市 | 市原市 | |||
| 野田市 | 松戸市 | 流山市 | |||
| 八千代市 | 佐倉市 | 船橋市 | |||
| 市川市 | 茂原市 | 成田市 | |||
| 我孫子市 | 印西市 | 習志野市 | |||
| 浦安市 | 木更津市 | 匝瑳市 | |||
| 富里市 | 白井市 | 旭市 | |||
| 栃木県 | |||||
| 宇都宮市 | 佐野市 | 那須塩原市 | |||
| 小山市 | 栃木市 | 足利市 | |||
| 鹿沼市 | 真岡市 | 大田原市 | |||
| 下野市 | 日光市 | ||||
| 群馬県 | |||||
| 太田市 | 伊勢崎市 | 前橋市 | |||
| 高崎市 | 桐生市 | 渋川市 | |||
| 藤岡市 | |||||
| 茨城県 | |||||
| 水戸市 | 古河市 | 土浦市 | |||
| つくば市 | 日立市 | 牛久市 | |||
| 鹿嶋市 | 神栖市 | 石岡市 | |||
| 笠間市 | 守谷市 | 取手市 | |||
| ひたちなか市 | 那珂市 | 結城市 | |||
| 筑西市 | 小美玉市 | ||||
中部エリア
| 新潟県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長岡市 | 新潟市 | 上越市 | |||
| 燕市 | 三条市 | 新発田市 | |||
| 村上市 | 柏崎市 | ||||
| 長野県 | |||||
| 長野市 | 松本市 | 上田市 | |||
| 飯田市 | 佐久市 | 伊那市 | |||
| 安曇野市 | 塩尻市 | 茅野市 | |||
| 石川県 | |||||
| 金沢市 | |||||
| 富山県 | |||||
| 富山市 | |||||
| 岐阜県 | |||||
| 岐阜市 | 可児市 | 大垣市 | |||
| 関市 | |||||
| 静岡県 | |||||
| 富士市 | 浜松市 | 静岡市 | |||
| 藤枝市 | 磐田市 | ||||
| 愛知県 | |||||
| 岡崎市 | 安城市 | 豊田市 | |||
| 春日井市 | 一宮市 | 西尾市 | |||
| 瀬戸市 | 名古屋市 | 豊橋市 | |||
| 東海市 | 江南市 | あま市 | |||
| 稲沢市 | 小牧市 | 豊川市 | |||
| 半田市 | |||||
| 三重県 | |||||
| 津市 | 鈴鹿市 | 伊勢市 | |||
| 松阪市 | 伊賀市 | 名張市 | |||
| 桑名市 | |||||
近畿エリア
| 大阪府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 高槻市 | 岸和田市 | |||
| 堺市 | 和泉市 | 箕面市 | |||
| 豊中市 | 枚方市 | 八尾市 | |||
| 吹田市 | 宝塚市 | 三木市 | |||
| 京都府 | |||||
| 京都市 | |||||
| 奈良県 | |||||
| 奈良市 | |||||
| 和歌山県 | |||||
| 和歌山市 | |||||
| 兵庫県 | |||||
| 姫路市 | 明石市 | 神戸市 | |||
| 高砂市 | 西宮市 | 川西市 | |||
| 三田市 | |||||
| 鳥取県 | |||||
| 鳥取市 | 米子市 | ||||
中国・四国エリア
| 広島県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 福山市 | 府中市 | |||
| 東広島市 | |||||
| 岡山県 | |||||
| 岡山市 | 倉敷市 | ||||
| 山口県 | |||||
| 山口市 | 周南市 | 宇部市 | |||
| 防府市 | 岩国市 | 下関市 | |||
| 島根県 | |||||
| 松江市 | 出雲市 | ||||
| 香川県 | |||||
| 高松市 | |||||
| 愛媛県 | |||||
| 松山市 | 今治市 | 西条市 | |||
| 高知県 | |||||
| 高知市 | |||||
九州エリア
| 福岡県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | 北九州市 | 久留米市 | |||
| 飯塚市 | 宗像市 | 春日市 | |||
| 長崎県 | |||||
| 長崎市 | 大村市 | ||||
| 大分県 | |||||
| 大分市 | |||||
| 宮崎県 | |||||
| 宮崎市 | 登米市 | ||||
| 熊本県 | |||||
| 熊本市 | 八代市 | ||||
| 鹿児島県 | |||||
| 霧島市 | 鹿屋市 | 鹿児島市 | |||
| 沖縄県 | |||||
| 沖縄市 | |||||
